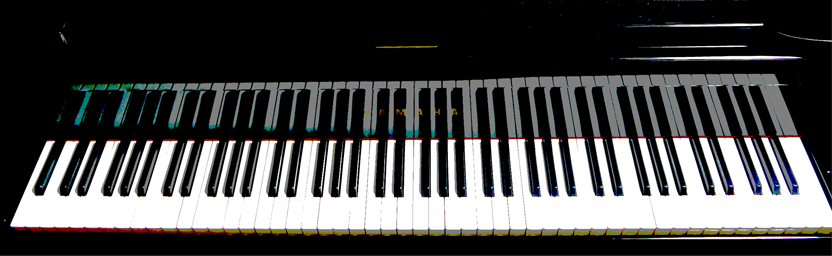音楽リテラシー講座
モノフォニー、ポリフォニー、ホモフォニーの違い |
| 第二回 |
| 音楽のテクスチャー |
コード理論大全には様々な和声手法が紹介されていますが、もちろんこの世の音楽理論の全てが記されているわけではありません。コード理論大全に含まれている内容はホモフォニックテクスチャー(Homophonic Texture)かつ、トーナルミュージック(Tonal Music)に限定されています。
現代で非常に有名なモノフォニックテクスチャーを中心とした楽曲としてはBlacks SabbathのIron Manが知られています。
この曲の大部分は伴奏が無く、ギターとベースとヴォーカルのユニゾン(同一のメロディを演奏すること)となっています。モノフォニックテクスチャーは他のテクスチャーに比べて非常に単純な構造ですが、使い方次第ではIron Manのように力強い印象を聴衆に感じさせるものとなります。 バッハはインベンションやフーガといった作品で、二つ以上の異なるメロディを組み合わせて和声進行を作り出す名手として、現代でも音楽の学習には欠かせない作品をいくつも残しています。このように複数の旋律で和声進行を作り出す手法は体系化され、対位法(Counterpoint)と呼ばれています。 日本国内に目を向けてみると、Blankey Jet CityのSkunkでは冒頭に現れるギターリフに被さるように別メロディのヴォーカルラインが同時に現れます。 Skunkに現れるポリフォニーは短いものですが、一方の声部の動きが大きいときにはもう一方の声部の動きは少なく、また反行(Contrary Motion)が多く含まれているなど、ペンタトニックスケールを中心とししながらもウィットに富んで耳に残るフレーズとなっています。 最後にホモフォニックテクスチャーについて紹介します。現代では最もよく聞かれる、一つの旋律と和音による伴奏によって組み立てられるテクスチャーをホモフォニックテクスチャー(Homophonic Texture)と言い、ホモフォニックテクスチャーに基づく音楽をホモフォニー(Homophony)と呼びます。つまりコードシンボルとメロディによって記述(リードシートによる記述)が出来る音楽というのは、このホモフォニックテクスチャーに限ります。ホモフォニックテクスチャーによる楽曲は非常に多く、それこそテレビから聞こえてくる音楽の90%以上を占めているのではないでしょうか。 コード理論大全では楽曲を主にメロディとコードシンボルを用いて解説していくので、取り扱われるテクスチャーは主にこのホモフォニックテクスチャーとなります。しかしながら、本書にはポリフォニーの要素が入っていないわけではありません。例えば伴奏の声部の動きを五線で説明する際に、順次進行による滑らかなヴォイスリーディングを得るための解説を行っています。伴奏の各声部を取り出していけば、声部一つ一つが旋律になっているので、複数のメロディを同時に扱うポイントも少なからず本書には含まれています。 現代においてホモフォニックテクスチャーの学習が和声学(Harmony)の学習であるように、ポリフォニーの学習と対位法の学習は同義と言っても過言ではないでしょう。対位法の本来の目的は複数の旋律のみで和声を表現するというところにあります。つまり表現すべき和声の何たるかを理解していないと、対位法の技術は習得できないのです。 例えばコンニャク農家がラーメンと同じ食感の糸コンニャクを研究開発するためには、中華麺がどんな食感であるかを理解していないと、その食感の再現は不可能と言えるでしょう。つまり対位法で表現したいと思うレベルの和声を完全に理解してからでないと、対位法の学習には意味がないのです。コード理論大全はホモフォニックテクスチャーを中心に音楽理論を取り扱っていますが、いずれは和声と対位法を同時並行に学べる教科書を書ければと考えています。 |
| Tweet |
※著者作品(CD・楽譜)のご注文はこちらから 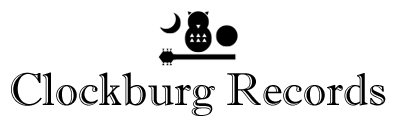 |