音楽リテラシー講座
ベルリオーズ、ショパンの手法 |
| 第五回 |
| 調性を超える試み − 前期ロマン主義時代 |
前回、現在のトーナルミュージックの理論はブラームス、ワーグナーが活躍した頃に完成されたという話をしました。ですので、いわゆる音楽大学の1〜2年時に習う古典的な和声学の教科書にはロマン主義時代後期以降の和声の内容については基本的にはあまり多く触れられていません。しかしながら19世紀後半から現代に至るまで、古典和声学では説明できない音楽が作り出されてきました。今回は作曲家達がどのようにして、トーナルミュージックを超える音楽を生み出していったか、考察、解説をしていきます。 トーナルミュージックを超える音楽の試みとして、まず初めにエクトル・ベルリオーズによって1930年に作曲された『幻想交響曲』を挙げておきます。この曲は演奏頻度が高く、日本でも非常に人気のオーケストラ曲となっています。1930年といえばベートーヴェンの没後からまだ3年しか経っておらず、ロマン主義時代全体でみると、初期〜中期にあたります。ですので、幻想交響曲には古典派の影響がまだまだ残されています。ただし宮廷作曲家の交響曲には見られないような、ベートーヴェン的とも言える勇壮なオーケストレーションが随所に現れます。その中で初期ロマン派作曲家達の作品と決定的に異なる和声手法としては、第五楽章でグレゴリオ聖歌の一つ『Dies Irae(怒りの日)』をメインの旋律として取り入れている事です。
怒りの日で使われているスケールは、ナチュラルマイナースケールの第六音を半音上げたドリアンスケールです(ただし幻想交響曲内で使われているメロディは第六音が強調されたものではありません)。ドリアンスケールでは主音へのトニシゼーションが行われていません。古典派や初期ロマン派の短調の音楽では主音に戻る際に第七音を半音上げ旋律や和声に導音を作りますが、このDies Iraeの引用では導音が用いられていないのです。別の言い方をすると、通常はトニックコードであるI-に戻る際には和声的短音階、もしくは旋律的短音階を用いるところ、この幻想交響曲の第五楽章に現れる旋律はそのセオリーを無視しているのです。 このように、既に完成しつつあるトーナルミュージックの理論体系に聖歌という別の音楽要素を取り入れたことに和声的に重要な意味が存在しています。余談ではありますが、幻想交響曲で取り上げられたことをきっかけに、Dies Iraeのメロディはリストをはじめとする後の多くの作曲家にも引用されるようになりました。しかしながら幻想交響曲ではDies Iraeの引用部分はモノフォニックテクスチャーが採用されており、和声法としてトーナルミュージックを超える新たな手法が開拓されたとまでは言えないように思えます 和声学や音楽の歴史の教科書では私自身あまり目にしたことはないのですが、1939年に完成したショパンのプレリュードOp.28、第二番はその時代から考えると、非常に革新的な和声法を用いて作曲されたと言えます。この曲はシンプルに左手が伴奏、右手が旋律をそれぞれ担当していますが、左手の伴奏は楽譜だけを素直に捉えてしまうと不協和音の連続となっています。
しかしながら注意深く各和音に着目してみると、伴奏に含まれる音のうちの1音は他の音に対する隣接音となっており、この隣接音を除くと多くの箇所は三和音と三和音の転回系としてアナライズすることが可能です。通常非和声音である隣接音は主たる和音構成音を阻害しないように補助的に加えるものですが、この曲の場合は隣接音とその隣接音に隣接する和音構成音を一対一、もしくは一対二という高い比率で使用しています(第一小節目のA#対B、六小節目のEb対Eなど)。伴奏内に大胆に非和声音である隣接音を組み込むことにより、古典派音楽では聴かれなかった高い緊張感を作り出しています。 さらにこの曲はAマイナーで終始する曲ですが、冒頭部分から中盤までにかけては、EマイナーやGメジャーといった調性を強調しています。転調はバロックや古典の時代にも頻繁に用いられた手法ですが、通常曲の最初と最後は同一の調となります。しかしながら、この曲の場合は冒頭と終盤で調が異なっています。ベートーヴェンの没後約10年で驚くような和声の進化を感じられる作品ですが、あまり和声の教科書では取り扱われない傾向にあるのは非常に不思議です。 |
| Tweet |
※著者作品(CD・楽譜)のご注文はこちらから 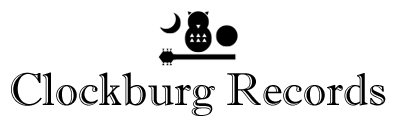 |

